ワガママLabでは、2022年から地元出身の学生を対象としたUターンや関係人口施策、高度デジタル人材育成支援として「MIT App Inventor」を活用したプログラムを全国で展開しています。
現在の日本では未曾有の少子化が加速しており、2022年の出生数は77万人。地方では学校の統廃合や既存産業の担い手不足など、これまでの社会システムを維持することが難しくなってきている現状があります。
地域から都市圏へ若者たちの流出が加速していますが、そのなかには地元で暮らし続けたいと思っている若者たちも多く含まれています。
若者たちが地元で学びたい環境、挑戦できる環境、働きたいと思う環境をつくることが、若者たちにとって暮らし続けたい魅力的なまちづくりにつながり、それに貢献するのがワガママLabです。
▼ワガママLabホームページはこちら

地元で暮らす人たちの困りごとを解決するアプリをつくる、高度デジタル人材育成プログラム
ワガママLabは、地域で暮らす人たちの困りごとを解決するアプリをつくるプログラムです。
これまで各地で中学生、高校生、大学生などを対象に開催し、地域で暮らす人たちが日々の生活の中であきらめていることや我慢していること(ワガママ)を可視化し、ワガママを叶えるアプリをつくるプログラムを実施してきました。
自分が地元で生まれ育った背景や感じてきたこと、学んできたことも活かしながら地域の人のためのアプリを開発し、実際に使ってもらうことで地域課題解決につながっていることを体験してもらいます。
そんな体験を通じて、デジタル技術を学べば将来的に地元に帰っても挑戦できる可能性に気がついたり、地元に暮らしながらデジタルを活用した仕事をするイメージを具体的に持つ学生が増えてきました。
送り迎えをしてくれるお母さんの負担を軽くするアプリ「ほこのってぃ」
茨城県鉾田市では「駅まで送り迎えをしてくれるお母さんの負担を軽くするためのアプリ」を、鉾田市出身の大学生チームがつくりました。地元でのつながりを活かし、駅までの送り迎えを近所の人たちで助け合う仕組みをつくることに挑戦しました。


▼アプリの紹介記事はこちら
MIT App Inventorとは

使用する「MIT App Inventor(MITアップインベンター)」とは、マサチューセッツ工科大学(MIT)が提供する、直観的なプログラミング環境で誰でもスマートフォンやタブレット用のアプリを作成できるソフトウェアです。
デジタルに詳しくなくても短時間で最初のアプリをつくることができます。その理由はMIT App Inventorが、年齢を問わず、どこにいても、誰もが、自分や周囲の人たちの生活を変えることができる地域課題の解決者になることを応援したい、という思想のもと設計されているからです。
実際に海外では、小中学生たちが生活水道の汚染による健康被害から住民を守るためのアプリをつくったり、水汲みの混雑を緩和するアプリをつくったりと、実際の生活の中の課題を自ら解決するために世界中で活用されています。
ワガママLabではMITに認定された教育モバイルコンピューティング マスタートレーナーである石原氏と連携して、ワガママLabプログラムの開発や普及活動を行っています。

マサチューセッツ工科大学認定
教育モバイルコンピューティング マスタートレーナー
ワガママLabコンテンツ開発ディレクター
トレーナー研修(プログラム開発/指導)
石原 正雄 氏
ボストン大学大学院修士課程修了。日本でのスクラッチやレゴマインドストームの普及に携わる。コンストラクショニズム(構築主義)に基づく教育学実践と教材開発をミッションとし、STEAM教育と人開発・組織開発に注力。日本で唯一のマサチューセッツ工科大学から教育モバイルコンピューティングマストレーナーに認定を受けています。
地元の課題解決に挑戦することは、世界と繋がる。App Inventor財団との連携
MIT App Inventorはアメリカに拠点を置く非営利組織App Inventor財団を中心に、世界中で推進されています。ワガママLabもApp Inventor財団と連携しながら日本で推進しています。
2022年度に茨城県鉾田市で実施した「ほこたワガママLab」が、日本の活動で初めて、App Inventor財団が運営するメディアに取り上げられました。
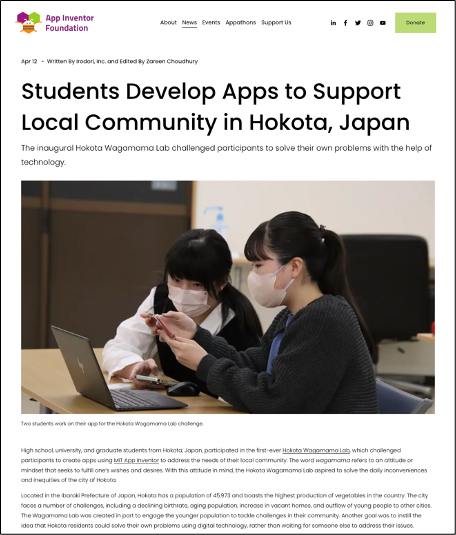
記事はこちらです。
https://www.appinventorfoundation.org/news/wagamama-lab
ほこたワガママLabの成果発表会「wagamama awards」では、App Inventorのエグゼクティブディレクターであり、MIT APP Inventor財団事務局長のNatalie Lao,PhD(ナタリー・ラオ博士)から激励のメッセージをいただきました。
Natalie Lao,PhD
Executive Director of the App Inventor Foundation
MIT APP Inventor財団事務局長
▼hokote wagamama awardsレポートがこちら
地域課題を解決に挑戦することは地域の関係者だけでなく、世界にも繋がることができる。
そんな体感をすることで、地元を出ないと挑戦ができない・働くことができないと思っていた学生たちが、地元への認識が変わっていくのがワガママLabです。
高度デジタル人材育成プログラム「ワガママLab」の進め方
地域ごとに現状を踏まえながら、下記の流れで実施いたします。
- STEP1:プログラムの構築
地域で活動する学生、地域にゆかりがある学生と連携し、デジタルを活用した地域課題解決のプログラムを構築します。地域に若者の新たな挑戦が始まることを関係者に周知し、サポートする土台づくりを行います。
- STEP2:説明会・体験会
「なぜやるのか」という背景を前面に出した発信を行い、すでにデジタルに関心がある学生だけではなく、多様な興味関心を持つ学生にも参加を訴求できるように説明会や体験会を行う。
- STEP3:アプリ開発講座・フィールドワーク
地域で暮らす人たちの課題を解決するためにアプリ開発をMIT App Inventorを利用して行います。「誰のどんな課題を解決するのか」を突き詰め、自分ができることを実行します。つくったアプリを市民の方に生活の中で使ってもらうフィールドワーク等、実証実験を実施します。
- STEP4:最終報告会(wagamama awards)
地元の若者たちがデジタル技術を活用して、地域課題を解決するアプリ開発報告会を開催します。国内や海外で地域課題解決に取り組む若者などもオンラインで参加してもらい、地域課題を解決することは世界にも繋がること、地元でデジタルを活用した挑戦の可能性を体感してもらう場とします。
各地のワガママLab事例
各地で行った事例をご紹介します。
鉾田市:地元の高校生と大学生による地域課題解決「高度デジタル人材育成事業」
茨城県鉾田市は野菜産出額が日本一の地域です。地域の多くの事業者が一次産業であり、若者が働く場所は実家の農家を継ぐか市役所、JAなどの公共機関に勤めるのが主な選択肢となっています。しかし鉾田市は地域資源が豊富であり、地元に誇りを持つ人たちが多い地域です。そこで、地元で暮らす中高生や鉾田市出身の大学生を対象に高度デジタル人材育成支援事業「ほこたワガママLab」を実施し、若者たちがデジタルスキルを身につけることで地元で暮らし続けることが可能だということを実感する機会をつくりました。


須賀川市:地元の中高生を対象にした「まちづくりDX人材育成プロジェクト」
福島県須賀川市では国土交通省の官民連携まちなか再生推進事業の一環で「須賀川ワガママLab」を推進。地元で暮らす中学生・高校生が地域課題をスマートフォンアプリを開発し解決していく活動に挑戦しています。中高生にとっては地元の課題解決に取り組む挑戦をする経験が、地元のことを深く知り、大人になっても須賀川市に住み続けたいと思えるきっかけとなり、UIターンの促進につながる可能性がある事業として推進しています。


桑名市:小中学生の親子を対象にした地域課題解決スマートフォンアプリ開発講座
三重県桑名市でも若者が進学を機に都市部に出て行ったきり、地元に戻って来れないことが大きな課題としてあります。そこで小中学生を対象に、親子で桑名市における地域課題を学び、課題解決に向けたスマートフォンアプリを開発する1日の体験会を実施。参加者にとってはデジタルスキルを身につけることができれば、地元で暮らしながらも働くことができるという新たな可能性を親子で感じてもらえる体験となりました。


体験会なども実施しています。お気軽にお問い合わせください。
下記フォームからご連絡お願いします。
お問い合わせフォーム
